
問いをつくれ。
社長ブログ
「3人に1人」が知っている
2015-01-22
外部機関を使って、「公募」と「公募ガイド」に関する市場調査を実施しました。
主目的は、雑誌のリニューアルに向けた現状把握です。
調査項目は多岐に渡りますが、
その中には「公募ガイド」に関する認知度も含まれています。
で、気になる結果ですが、
「月刊公募ガイド」の認知度は、おおよそ「3割」というものでした。
では、
この「認知度=3割」というのは、高いかのか、低いか。
オンライン通販のamazonは8割超と思われますが、
色々な新製品の認知度で3割を超えてくるものは、そうはないでしょう。
日経産業地域研究所の最新調査によれば、
エリクシール(資生堂)=35.0%
iPadエア2(アップル)=33.6%針なしステープラー「ハリナックスプレス」(コクヨS&T)=24.6%
ということですから、
個別の雑誌銘柄で「3人に1人」という認知は、
これまでマーケティング的な施策をほとんどしていないことを考えると、
必ずしも低いわけでもなさそうです。
その他、公募ガイドの認知について特徴的だったのは、
40代後半から50代前半をピークとした、
「逆スマイルカーブ」を描いていたということでしょうか。
雑誌市場のピークが1997年ですから、今から約20年前。
その時に30歳前後だった方たちの認知が一番高く、
そこから離れるに従って漸減する結果を示していました。
これは定期的に実施している「読者調査」とはちょっと違った傾向だったので、
その意味と対策を考えてみたいと思っています。何事もなかったかのように、淡々と。
2015-01-21
以前ブログでご紹介した、
鉄道会社のフリーペーパーの最新号が配布されていました。
岩崎俊一さんの連載エッセイがどうなるのか気になっていたので、
手にとって誌面をめくってみたところ、
定位置には別のエッセイが掲載されており、
誌面の最後に「謹告」として訃報について触れられていました。
おそらくですが、
岩崎さんのご訃報は、単に年末年始の代原問題ということだけでなく、
編集部にとってそれなりのインパクトがあったと思います。
一方で、読者にとってはそんなことは関係なく、
「面白いか、どうか」がすべてなので、
「何事もなかったかのように、淡々と」
すすめる必要があったのですが、
同業者としても、その対応に着目していました。
翻って考えてみると、公募ガイドの創刊30周年関連のイベント、
賑やかしであれやこれややるのではなく、
プロとして「何事もなかったかのように、淡々と」読者メリットを追求し続けるのがよいのではないかと、
ちょっと思ってしまいました。「魂の入った」事業計画
2015-01-20
現在、新年度の予算を策定しています。
公募ガイド社は12月決算なので、
本来であれば、予算は昨年末には出来上がっていないといけません。
ただし、今回からは当事者意識の醸成を目的に、
ボトムアップ型で策定したいと考えていて(その為には時間が無さ過ぎた)、
資金繰りだけキッチリ押さえて、年明けに腰を据えて予算策定することにしたのです。
資金調達、IRなど、事業計画や予算を策定する目的は様々ですが、
要は、
「目指すべき目標」と「実現に向けた手段」をハッキリさせ、
事業の成功確率を高める
(よく”蓋然性”という言葉が使われます)
ということです。
山登りに例えれば、
登りたい山は、エベレストなのか富士山なのか、
登山ルートはどうするのか(頂上を目指すルートはひとつではない)、
そのためにはどんな装備を準備しておけばよいのか(いくら掛かるのか)、
というイメージでしょうか。
ただし!です。
本当に「魂の入った」事業計画となると、これはもう滅多にお目に掛かれません。
コンサル歴も20年近くになり、事業部レベルのものも含めれば、
少なくとも1,000件以上の事業計画を見たり、作ったりしてきましたが、
残念ながら、絵に描いた餅、単なるエクセルの計算、に留まってしまうものがほとんどです。
よく言われる問題点としては、
「会社・事業に対する理解」と「事業計画策定ノウハウ」の両立
で、それはその通りとは思うのですが、
最終的に「魂が入るかどうか」は、「どこまで当事者意識があるのか、ないのか」、
そこに尽きる気がします。
人のお金でサラリーマン的に事業をやるのと、身銭を切って一世一代の勝負をするのとでは、
当たり前ですが、感覚が全く違います。
これはもう、本当に研ぎ澄まされます。
「零細企業の資金繰り感覚の事業計画」と言えば、伝わるでしょうか。
そういう私も、一年前、外部の人間として公募ガイド社の事業計画を作りましたが、
今からみれば、全然ダメですね(笑)
「社員の一人一人に、どこまで当事者意識を持たせられるか」
今回の予算策定の最大テーマです。
※まずは富士山を目指したい。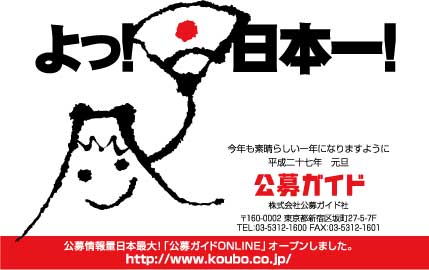
幻のラジオ体操「第3」
2015-01-19
仕事柄、自治体の広報誌、フリーペーパーには、
なるべく目を通すようにしています。
公民館や路上に設置されている「地域の掲示板」の前を通りかかったら、
立ち止まってチェックするのも習慣化しています。
週末にゆっくりとジョギングしていたら、
路上の地域掲示板に変わったお知らせを見つけました。
「”幻のラジオ体操第3”で健康づくり」
えっ、なに、ラジオ体操に「第3」ってあるの?
そのチラシによれば、ラジオ体操第3は、・1946年(昭和21年)に製作され、ラジオで1年半あまりしか放送されなかったため、
「幻のラジオ体操」と呼ばれている
・第1、第2に比べるとテンポが速く、手を伸ばしたりジャンプするなどの動きがダイナミックな点が特徴
とのこと。気になってラジオ体操のことをちょっと調べてみると、
さすがに歴史があって奥が深いです。
全国ラジオ体操連盟
NHKテレビ・ラジオ体操
かんぽ生命 ラジオ体操・みんなの体操
なんと昨年には、「第1回 全国小学校 ラジオ体操コンクール(かんぽ生命)」が開催されています!
今年も第2回を開催予定とのことなので、
要項が発表されたら、公募ガイドONLINEにアップしたいと思います。
※ネット情報では、「ラヂオ体操第4」というパロディがあるらしいです。
(難しすぎて、とてもできない)
キング・カズ
2015-01-16
昨日の夜のテレビ番組で、
サッカー選手の三浦知良さんが取り上げられていました。
内容的には大よその方が予想できるとおり、
「47歳になってもJリーグで現役を続けられる、その秘訣」
といったものではあるのですが、何か見てしまいます。
イチロー選手や葛西選手なんかもそうですね。
47歳で現役プロサッカー選手ということは、
ビジネスで言えば、「90歳でバリバリの記者」とか「100歳で法廷に立ち続ける弁護士」とか、
そんな感じなのでしょうか。
いやいや、すごいです。
カズ選手と言えば、その「名言」でも有名ですが、
日経朝刊に「サッカー人として」というコラムを掲載されています。
たぶん、第2・4金曜掲載なので、
「今日は載っているかな」と思って見てみましたが、見あたりませんでした。
電子版やバックナンバーでは読めないようなので、
興味ある方は気にして見てもらえればと思います。
(新潮新書から書籍化されているようですが)
※それにしても。
芥川賞・直木賞の発表翌日のブログネタが「キング・カズ」って・・・
公募ガイド社の社長としては、どうなんでしょう??
雨が降ったら公募ガイドは売れる?
2015-01-15
東京は朝から久し振りに雨が降っています。
雨が降ると売り上げが「下がる」商売と「上がる」商売があると思いますが、
本屋さんは雨が降るとお客さまが増える業種のひとつと言えます。
他には喫茶店、映画館なんかもそうでしょうね。
雨が降る
↓
インドアの時間が増える
↓
読書や創作の機会が増える
ということなので、公募ガイド的にも「雨はウェルカム」ということになるのでしょうか。
話は変わりますが、
「公募ガイドが最も売れる月」
って何月だと思われますか?
答えは、「8月号(7月9日発売)」です。
理由は夏休みがあるからです。
夏休みをターゲットとした公募案件が増えますし、
読者も「せっかくの休みだから、何かやってみるか」という気になるのでしょう。
もともと読書をするタイミングとして、
「自宅でくつろいでいる時」
という方が圧倒的に多い(読書世論調査)わけですから、
弊誌に限らず、「家にいる時間が増えるほど、本は読まれる」
ということなのですが、
「公募」という取扱いジャンルの特性上、その傾向が強くなるということだろうと思います。
今後、もっと掘り下げて研究してみたい分野です。
※飲食系は、天気より気温の昇降が売れ行きを大きく左右します。
出典:日経レストランテーパリング
2015-01-14
エントリーしている別府大分毎日マラソンまで、残り3週間を切りました。
この時期に入ると、ガンガン走り込んで脚力と心肺を鍛えるフェーズは終了し、
「テーパリング」と呼ばれる調整フェーズに移行します。
トレーニングの量を徐々に減らし(ただし、強度は落とさない)、
体をピークの状態にもっていくためのメニューに切り替えていきます。
要は、
「ここまできたら、もう強くなるのは諦めて、
いま持っている力を最大限発揮できるように、体調を整えることに集中する」
ということです。
ですので、
・手洗い・うがいの励行、人混みを避ける(風邪やインフルエンザの徹底予防)
・禁酒こそしないが、プライベートな飲み会は極力がまんする(暴飲・暴食、深酒リスク)
・調子に乗って子供と遊具ではしゃがない(骨折、捻挫リスク)
というようなことにも気を使います。
「人事を尽くして天命を待つ」
ということわざが真にぴったりな時期に入ってきました。人生で一度きりのイベント
2015-01-13
昨日は成人の日でしたね。
たまたま、お昼時に駅ビルのレストランフロアに行ったのですが、
成人式帰りと思われる晴れ着やスーツ姿の男女を結構目にしました。
さて、お昼ご飯も食べ終わり、下りのエレベーターを待っていると、
すぐエレベーターそばの中華店の前で、
晴れ着姿の若い女性と店員と思われる40~50代の女性が何やら会話しています。
もう14時近かったので、「今日はレストランの順番待ちも大変だ」などと思っていたら、
着物姿の女性の目からポロリと涙が。
「えっ!?」と思ってしばらく遠目に眺めていると、
もう一人の女性がその子の頬をハンカチでふきながら、自分も泣いています。
「そうか、この二人は親子なんだ」
成人式の帰り、お店で働くお母さんに「ありがとう」を伝えに来たのでしょうか。
結婚式ではよく目にするシーンですが、
成人式でこのような光景を見たのは初めての気がします。
程なく来たエレベーターの中で自分の成人式を思い返してみると、
「そうだ、センター試験だった!」
大学入るのに2浪もしてしまったせいで、
宙ぶらりんのまま二十歳を迎えてしまい、日程が被ってしまったのです。
人生で一度しか経験できないイベントはいくつかあると思いますが、
成人式もそのひとつと思います。
自分にさっきの娘さんのような行動ができたとはとても思えないですが、
「こういうイベントは、面倒くさがらずに大事にした方が良いな」
と反省させられたのでした。
※「荒れる成人式」はメディアが取り上げなくなったおかげで減ってきたらしいです。
ロゴ、変わります(その2)
2015-01-09
昨年末から、あーでもない、こーでもないと検討していた雑誌ロゴの方向性が、
ようやく固まりました(ロゴ、変わります(たぶん))。
公募ガイドのロゴの変遷を振り返ってみます。
①創刊号~1986年秋号(VOL.4)
②1987年1月号(VOL.5)~1989年4月号(VOL.31)
③1989年5月号(VOL.32)~1990年6月号(VOL.45)
④1990年7月号(VOL.46)~1993年4月号(VOL.79)
⑤1993年5月号(VOL.80)~2002年1月号(VOL.185)
⑥2002年2月号(VOL.186)~2007年1月号(VOL.245)
⑦2007年2月号(VOL.246)~
第3代の「KOBO」はなかなか斬新です!
今となっては、大手ネット系企業から同名の電子書籍サービスが提供されているのも、何かの縁を感じます。
が、肝心の雑誌の売上は読者から「公募ガイド」と認知されずに激減したらしく(笑)、
第3代は短命に終わったようです。
第4代として第2代のロゴを再登板させたところ売上は元に戻ったらしいので、
「アイデンティティの変更は慎重に」という好事例と思います(笑)
それにしても、ロゴは好きなジャンルのひとつなので、
こうやって変遷を辿るのとか、けっこう楽しいですね。
第8代は2015年4月号から採用される予定なので、
どんな感じになるのかご期待下さい!戦略的カニバリ
2015-01-08以前のブログで書きましたが、ウェブサイトのリニューアルに続き、
雑誌の全面リニューアルを進めています(ロゴ、変わります(たぶん))。今、社内で問題となっているのが、
雑誌とウェブの「カニバリゼーション(共食い)」です。
「新店オープンしたら既存店とカニバって、売上が10%ダウンしてしまった」
というように、カニバリという単語は、一般的には悪い意味で使用されるケースが多いと思います。
これを弊社に当てはめて言えば、雑誌に載せるようなコンテンツをウェブで掲載
↓
雑誌の売上が落ちる
↓
売れない雑誌にはクライアントは広告出稿しないというのが想定リスクシナリオです。
ところが、実際にはカニバるとわかっていても、敢えて類似商品を投入するケースもあります。
どういうケースかと言えば、「自社既存商品とのカニバリリスク」 < 「他社商品からのシェア獲得」
というケースです。
つまり、「新商品は自社の既存商品の売上を下げるかもしれない。
でも他社のシェアを奪うことで、会社全体としての売上は増えるだろう」という場合においては、カニバリを戦略的に選択することもあるということです。
ただし、メニューやラインナップが増えるほど一般的には管理コストが増えるので、
最終的には、「売上(シェア)」と「コスト」の兼ね合いです。出版各社は、試行錯誤しながらも雑誌とウェブでそれぞれ工夫した展開を見せています。
当社も慎重かつ大胆な展開を推進したいと思います。



